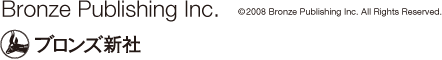奄美大島の画家といえば、田中一村だ。栃木県で生まれて、千葉で活動した後、50歳で奄美に移住して、69歳で亡くなるまで絵を描き続けた。
岩絵の具で描かれた亜熱帯植物やカラフルな魚は新鮮で、少し恐ろしい美しさがある。一村の絵を見ると、奄美は、1960〜70年当時と変わらない風景が残っていることがわかる。空港からほど近い場所には田中一村記念美術館もあり、何度も訪れてきた。適度にこじんまりとした美術館ながら、一村の幼少期の絵や書も展示してあり、見応えがある。
奄美の人たちにも、一村はとても身近な存在だったらしく、お年寄りからは、
「うちにも出入りしとったよ」
などと話を聞くこともある。
友人の先祖の遺影は、田中一村に描いてもらったもので、島民とも密接な間柄だったのだろう。
中心街にほど近いところに"田中一村終焉の家"がある。最期に過ごした家をそう遠くはない場所から移設したらしく、見に行くことにした。
住宅街からすこし登った坂の途中にあって、気づかず通り過ぎるところだった。人影はなく、緑に囲まれて暗く、急に湿り気を帯びる。外から見てもそう広くはなく、朽ちそうな木の隙間から少し中の様子がのぞけた。暗くてよくわからないが、古い奄美特有の、石の上に柱が乗せられた石場建ての木造家屋で、特別なことはなさそうだ。石に彫られた説明文が敷地内に置かれているだけで他になにもない。家の周りを一周したところで、ふと見知らぬおっちゃんが立っていることに気づいた。
「こんにちは」
と挨拶すると、おっちゃんは何も言わず、ちょいちょいと手招きをした。奄美ではよくあることなので、あまり警戒心もなくついていくと、隣の家へ入っていく。
「入っていいんですか?」
と聞くと、
「うん、入ったらドア閉めて」
とぼそぼそと言う。少しいぶかしがると、
「猫が逃げるから」
と言った。たしかに家の中には猫がいた。けれど、ドアの隣にある窓は全開で、どちらにせよ逃げるだろうと思い、おかしくなって笑う。だいたい庭にも家と垣根の隙間にも猫が何匹もいて、一体どれが飼い猫なのかわからない。そのまま居間のようなところに通されると、床の間を指さして、
「一村」
とつぶやいた。そこには水牛の角や写真、表彰状のようなものに混じって、額縁に入った1枚の絵があった。掛け軸のように長く、ソテツの木が描かれてある。墨にほんのすこし緑や黄色が混じったような色で、実を覆っている部分はヒヨコの羽毛のような柔らかさで描かれていて、確かにそれは一村の絵だった。
「すごい! 一村の絵がある!」
おっちゃんは笑っている。この絵が来た、いきさつか何かを説明してくれているのだとは思うが、方言とモニャモニャとした小さな声でよく聞き取れない。じっくり見させてもらい、おっちゃんにうながされて、外に出る。
「猫がいっぱいいるんですね」
などと話しながら、自然とおっちゃんのあとをついて歩き、そろそろ車に乗って出ようかな、と思ったところで、家の敷地の横に設置してある自販機をおもむろに触りながら、おっちゃんが言った。
「オゴラン?」
はじめは意味がわからず、聞き返すと、再び、
「オゴラン?」
と言う。よくよく考えてやっとわかった。飲み物を奢ってくれないか?と言っているのである。なるほど、一村の絵を見せてあげたかわりに、飲み物を買ってほしいと訴えている。その様子がなんともおかしくて、
「いいですよ。」
と言って、お金を入れると、冷たい缶コーヒーのボタンを押して、ニッコリと笑った。これで気が済んだと満足気な様子で缶コーヒーを飲みながら、家にもどっていった。
きっとおっちゃんは、観光客が"田中一村終焉の家"を見に来るたびに、家に招き入れて缶コーヒーを手に入れているのであろう。一見すると変な人に見られるかもしれない。でも、まるで子どもの発想を実行してしまうようなところがなんとも健気で、愛くるしい存在に思えてくる。それは島に存在すると言われている、子どもにいたずらをするのが好きな「妖怪ケンムン」のようだ。
だからわたしは、このおっちゃんのことを「妖怪オゴラン」と呼んでいた。また会ってみたくて、再び訪れたが、自販機はなくなっており、おっちゃんは現れなかった。本当に妖怪だったのかもしれない。
岩絵の具で描かれた亜熱帯植物やカラフルな魚は新鮮で、少し恐ろしい美しさがある。一村の絵を見ると、奄美は、1960〜70年当時と変わらない風景が残っていることがわかる。空港からほど近い場所には田中一村記念美術館もあり、何度も訪れてきた。適度にこじんまりとした美術館ながら、一村の幼少期の絵や書も展示してあり、見応えがある。
奄美の人たちにも、一村はとても身近な存在だったらしく、お年寄りからは、
「うちにも出入りしとったよ」
などと話を聞くこともある。
友人の先祖の遺影は、田中一村に描いてもらったもので、島民とも密接な間柄だったのだろう。
中心街にほど近いところに"田中一村終焉の家"がある。最期に過ごした家をそう遠くはない場所から移設したらしく、見に行くことにした。
住宅街からすこし登った坂の途中にあって、気づかず通り過ぎるところだった。人影はなく、緑に囲まれて暗く、急に湿り気を帯びる。外から見てもそう広くはなく、朽ちそうな木の隙間から少し中の様子がのぞけた。暗くてよくわからないが、古い奄美特有の、石の上に柱が乗せられた石場建ての木造家屋で、特別なことはなさそうだ。石に彫られた説明文が敷地内に置かれているだけで他になにもない。家の周りを一周したところで、ふと見知らぬおっちゃんが立っていることに気づいた。
「こんにちは」
と挨拶すると、おっちゃんは何も言わず、ちょいちょいと手招きをした。奄美ではよくあることなので、あまり警戒心もなくついていくと、隣の家へ入っていく。
「入っていいんですか?」
と聞くと、
「うん、入ったらドア閉めて」
とぼそぼそと言う。少しいぶかしがると、
「猫が逃げるから」
と言った。たしかに家の中には猫がいた。けれど、ドアの隣にある窓は全開で、どちらにせよ逃げるだろうと思い、おかしくなって笑う。だいたい庭にも家と垣根の隙間にも猫が何匹もいて、一体どれが飼い猫なのかわからない。そのまま居間のようなところに通されると、床の間を指さして、
「一村」
とつぶやいた。そこには水牛の角や写真、表彰状のようなものに混じって、額縁に入った1枚の絵があった。掛け軸のように長く、ソテツの木が描かれてある。墨にほんのすこし緑や黄色が混じったような色で、実を覆っている部分はヒヨコの羽毛のような柔らかさで描かれていて、確かにそれは一村の絵だった。
「すごい! 一村の絵がある!」
おっちゃんは笑っている。この絵が来た、いきさつか何かを説明してくれているのだとは思うが、方言とモニャモニャとした小さな声でよく聞き取れない。じっくり見させてもらい、おっちゃんにうながされて、外に出る。
「猫がいっぱいいるんですね」
などと話しながら、自然とおっちゃんのあとをついて歩き、そろそろ車に乗って出ようかな、と思ったところで、家の敷地の横に設置してある自販機をおもむろに触りながら、おっちゃんが言った。
「オゴラン?」
はじめは意味がわからず、聞き返すと、再び、
「オゴラン?」
と言う。よくよく考えてやっとわかった。飲み物を奢ってくれないか?と言っているのである。なるほど、一村の絵を見せてあげたかわりに、飲み物を買ってほしいと訴えている。その様子がなんともおかしくて、
「いいですよ。」
と言って、お金を入れると、冷たい缶コーヒーのボタンを押して、ニッコリと笑った。これで気が済んだと満足気な様子で缶コーヒーを飲みながら、家にもどっていった。
きっとおっちゃんは、観光客が"田中一村終焉の家"を見に来るたびに、家に招き入れて缶コーヒーを手に入れているのであろう。一見すると変な人に見られるかもしれない。でも、まるで子どもの発想を実行してしまうようなところがなんとも健気で、愛くるしい存在に思えてくる。それは島に存在すると言われている、子どもにいたずらをするのが好きな「妖怪ケンムン」のようだ。
だからわたしは、このおっちゃんのことを「妖怪オゴラン」と呼んでいた。また会ってみたくて、再び訪れたが、自販機はなくなっており、おっちゃんは現れなかった。本当に妖怪だったのかもしれない。