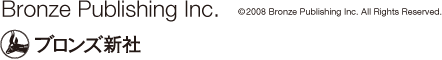今、フランスはパリから北、車で2時間半ぐらいのところ、アミアンという町にいる。アミアンという町のことは、名前ぐらいは聞いたことがあったけど、ほとんど何も知らない。なぜ、そんなところにいるかというと、そこに立派なサーカス劇場があって、そこでサーカスの演出をしているんだ。
今、フランスはパリから北、車で2時間半ぐらいのところ、アミアンという町にいる。アミアンという町のことは、名前ぐらいは聞いたことがあったけど、ほとんど何も知らない。なぜ、そんなところにいるかというと、そこに立派なサーカス劇場があって、そこでサーカスの演出をしているんだ。
なぜ、そんなことになったかというと、随分前から付き合いのある「シルク・バロック」というサーカスカンパニーの団長クリスチャン・タゲ氏から、演出をしないかと言われ、引き受けたから。
題材は、ブレヒトの『三文オペラ』あるいはその原作のジョン・ゲイの『乞食オペラ』。これを、1幕目を僕、2幕目をチリの演出家モリシオ・セルドンという人、3幕目はフランスの若い女性演出家カレル・プリュグノという人が、それぞれ構成演出をするという、タゲ氏の企画。お互いあまり打ち合わせなどしないで、それぞれが自分の世界をつくるようにと言われた。面白いような気もするし、大丈夫かなあと心配にもなる。モリシオという人の作品は観たことがあるけど、今回は一度も会っていない。カレルさんには去年の暮れに何回か会ったけど、彼女の作品は一度も観たことがない。
![]()
3月17日の昼に、成田からエールフランスに乗る。2日前に『ピランデッロのヘンリー四世』が松本で終わって、次の日は自宅の片付けをしたり、6月の『桜姫』の打ち合わせをしたりして、それから夜中に、バスルームでヘンリー四世の髭を剃って、バリカンで頭をくるくる坊主にして、そうだ、その前にこのブログ連載「ゴドーを待ちながら」が書きかけだったので、それを書いた。とにかく終わってしまった「ヘンリー四世」の余韻なんか感じる暇もなく、ほとんど寝ないで飛行機に乗ったので、まず、眠った。
シャルル・ドゴール空港から、ビルマレシャルという村のタゲの家に行く。すぐにアミアンには行かず、3日間はここで稽古することになったのだ。その村は、空港からパリの外側をぐるっと回って、ちょうど反対側の南にあるフォンテーヌブローの森の少し先。タゲの家は、広い畑のただ中にある大きな農家だったところで、納屋の一つがサーカスの練習場になっている。去年の秋には、ここでオーディションをした。そうそう、『破れ傘長庵』の稽古中に、4日間休みをもらってここに来て、今回のメンバー10人を選んだのだ。
そのあと、暮れからお正月にかけて、打ち合わせも兼ねて僕たち家族が10日ほどお世話になった。だから勝手知ったる他人の家、すぐにサーカスの気分が高まる。
モリシオ演出の第二部は、すでに南仏のほうでつくり上げているので、その映像を見せてもらう。体育館みたいなところで稽古着でやっているので、あまりよくわからないし、意識しないほうがよさそうなので、雰囲気だけをぼんやり眺めた。
![]()

 翌3月18日、みんなに会う。僕はタゲの住居である母屋に泊っているのだが、彼らは広い敷地に停めてあるいくつかのトレーラーハウスに泊っている。庭に集まってきたみんなに、僕の担当する第一部の構成と意図を話す。
翌3月18日、みんなに会う。僕はタゲの住居である母屋に泊っているのだが、彼らは広い敷地に停めてあるいくつかのトレーラーハウスに泊っている。庭に集まってきたみんなに、僕の担当する第一部の構成と意図を話す。
観たことがないはずなのに、なんだか知っているような、懐かしいサーカスの匂い......「この感じは何だ?」と観ている人たちが、それぞれこっそり感じるような始まりがよい。遠くからサーカスの音楽が聞こえてきて、夢みたいな呼び込みの声が聞こえて、10人の芸人たちが、荷車を曳いてゆっくり現れる。等身大の人形も混ざっている。ブレヒトの『三文オペラ』の幕開きの歌詞を、ハンドスピーカーで叫んでいる声が聞こえる。人々は緊張し、こそこそと辺りをうかがう。
「貧しきサルティンバンコたちよ、己の貧しさを示せ! それをショウにして楽しませてくれ!」
さらに、物語のあらすじを語る声が聞こえ、芸人たちは自分の手足をもぎ取ってジャグリングをしたり、アクロバットをしたりしながら、飛び跳ねる......そんな始まり。
2つ目の場面は、スラップスティックコメディ風ピーチャム氏の家庭劇。両親の知らないうちに、宿敵メッキーと婚約してしまった娘、ポリー。スラップスティックというのは、文字通り引っ叩く棒、道化なんかが持っていて叩くと、パン!と大きな音がする、まあ、張り扇みたいなものだね。無声映画時代に、マック・セネットという人がつくり上げたドタバタ喜劇のスタイルを、スラップスティックコメディという。
3つ目は、婚礼をあげたメッキーとポリーを仲間たちが、手荒く、サーカス風に祝うシーン。ここで、彼らの芸を披露しながら、みんな酔っ払っていく。主賓のメッキー、ポリーは、人形に演じてもらう。そして、客人が帰った後、2人きりになったポリーとメッキーの人形は、いつの間にか生身の芸人に変わっていて、甘苦しい愛のアクロバットになる......これが大まかな構成。
僕の持ち時間は27分。短いのか長いのか、サーカスを演出したことがないのでよくわからない。
みんな、これから1カ月、どんな稽古をしてどんなものが生まれるのか、日本から来た見知らぬ演出家が何を望んでいるのか、真剣に聞いている。
昼ごはんは、車で10分程、村の中心にある小さなレストランでみんなで食べる。
ビルマレシャルでは、みんなの様子を見るために、人形のまねをしてみたり、登場のちょっとしたイメージを話して、それを自分たちのサーカススタイルで表現してみるというようなワークショップ的な作業と、各自の技を訓練する時間にあてた。僕は彼らの身体能力と表現の可能性を確かめる作業をしていた。彼らの技にどれくらい頼っていいのかを測っていた。
![]()
4日目、いよいよアミアンへ行く。昼ごろ出発して、宿泊地のボーヴィルという村に2時過ぎに到着。アミアンの稽古場となるサーカス小屋から25キロも離れている。なんでそんなに遠い所に宿をとったのだろうと不思議になるが、みんなが一緒に快適に暮らせて、しかも経済的条件も折り合いのつくところをやっと見つけたのだろう。
このフランスの北のほうに近づくと、どういうわけか煉瓦造りの家が増えてくる。南のほうは、どちらかというと白っぽい大きな石でできている家が多いような気がするけど、こっちのほうは、赤茶色の煉瓦の家が多いのだ。僕たちが3週間お世話になる家も、レンガ造りの、以前農家だった建物で、入ってみるとなかなかしゃれている。レンガ造りの農家をそのまま改装して素敵な合宿所になっている。道に面した母屋は、タゲ氏と10人の芸人たちがいくつかの部屋に分かれてあてがわれ、僕と通訳兼演出助手のアケミさんとミュージシャンのフランソワとロロンが、中庭を隔てた離れの家に泊まることになる。その家は、以前大きな納屋だったものを工夫して改装したものなのだ。そのさらに奥には、また庭があって、ガチョウや鶏がいる。
僕はこの家屋がとても気に入った。煉瓦の納屋のような建物はまだ昔のままになっているところもあって、薪が積んであったり、農具のようなものが押し込んであったり、鉄の柵扉がいくつか並んでいるのでなんだと思ったら、食用の兎小屋だったのだという。いろんなところを探検したり、生えている草花や家畜を眺めるのは楽しい。とにかく、わずか3週間だが、こんなところに住めるのかと思うとうれしくなる。

 翌日、稽古場となるサーカス劇場に行く。石造りの立派なサーカスのための専用劇場。今日は4本のポールを立てたり、持ち込んだマットや道具類を並べたり、明日からの稽古の準備。
翌日、稽古場となるサーカス劇場に行く。石造りの立派なサーカスのための専用劇場。今日は4本のポールを立てたり、持ち込んだマットや道具類を並べたり、明日からの稽古の準備。
ここのサーカス劇場の支配人が、劇場の歴史をうれしそうに説明してくれる。そもそも、19世紀フランスには、たくさんのサーカス小屋があった。何百もあったそうだ。それは半分遊園地のような、見世物小屋のような、食べ物屋も一緒になった、アトラクション会場、娯楽施設のようなものだったらしい。とにかくそういうものがフランス全国に流行って、そこで、曲馬や軽業も行われた。でも19世紀後半になると、だんだんすたれて、木造だったものはどんどん壊されてしまう。
その頃、アミアン市の市議会にジュール・ヴェルヌという人がいて、サーカスがとても好きだったので、どうしてもこのサーカス劇場をきちんとした石造りの劇場にしようと努力した。ジュール・ヴェルヌって、誰だっけなあ......えーと、聞いたことあるぞ、と思っていたら、ほら、『八十日間世界一周』や『海底二万里』とかそういうのを書いた空想科学小説の父みたいな人だった。僕は子どものころ『十五少年漂流記』という本を読んで、すぐにも友だちと冒険旅行に行きたくなったことを覚えている。眠れずに、布団の中で朝まで空想旅行をしていたころのことを覚えている。アミアンにサーカス劇場をつくったのが、あの『十五少年漂流記』の作者だったのか!
こういう古典的なサーカスの劇場は、フランスにもほとんど残っていない。前にパリの「シルク・ディヴェール」というサーカス劇場に行って感動したことがある。出しものもよかったけど、劇場の佇まいがよかったんだ。映画『フェリーニの道化師』は、てっきり「シルク・ディヴェール」で撮影されたのかと思っていたが、ここだった。アミアン市民に、「シルク・ド・ジュール・ヴェルヌ」と呼ばれ親しまれている、このサーカス劇場だった。
勾配の急な、真っ赤な椅子が並んでいる客席は2000人入るという。真中に直径13.5メートルの円形舞台(この大きさは、馬の都合でサーカス小屋の決まりなのだ)。高い天井。舞台裏には人間と馬たちの楽屋。動物の匂いが染みついている。コンクリートと無骨な鉄骨。建築は、エッフェル塔を設計したエッフェルさんの弟子。出来上がったのは1889年。たぶんエッフェル塔と同じ年じゃないかな?
まあ、そんなことはどうでもいいのだが、僕はこの劇場の中にいるだけで、なかなかうれしくなり、興奮する。前に『コーカサスの白墨の輪』という芝居をつくったのだけど、劇場の中に理想の劇空間をつくるのに苦労して、とうとう最終公演地の松本で、大劇場の舞台の上に、客席600の仮設円形劇場をつくった。どうやら僕は、こういう空間で芝居をしたいらしい。というか、こういう空間が似合うような芝居をつくりたいらしい。と、うすうす思う。
![]()
ここでのサーカスの稽古日誌のようなものを書いてみようと思ったが、他人に伝えようと思うと、自分のやっている作業は実に淡々とした変化の見えないものなのだと気づく。芝居の稽古も同じで、いつも以前の手帳を見ると、どの日もただ、「稽古」としか書いてない。それなのに明らかに、始めた時点と終わりでは、まるで違うものが生まれている。それをそのとき、その時点で高速写真のように自分の作業を見つめることはできない。強いて言えば、始まりのころのプランと、最後の駆け上っていくような、奇跡の時間は、自覚することができる。でも、ほとんどの稽古時間は、何が起きたのか思い出せない。僕にとっては、ものづくりの作業はそんなものだ。「なんだい、つまんないなあ」と思うのなら、ごめんね。
「シルク・ド・ジュール・ヴェルヌ」で僕の担当した27分のサーカスは、コツコツとスープを煮込むように、繰り返しながら少しずつ出来上がる。すこーし焦ったり、すこーし安堵したり、たまーに怒ったり、興奮したり、と自分では感じるのだが、どうなのだろ? 「何を言っているんですか!」という声が聴こえるような気もする。