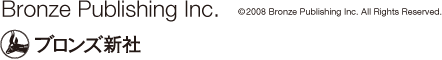ジャックが頬杖しながら僕のほうを見ているので、今度は僕が話をしなければならない番らしい。で、僕はちょっと人形の話をしようと思う。
ちょうど何日か前に、結城座という人形劇の一座と一緒に芝居をして、終わったばかりだしね。そう、役者は僕ひとりで、あとはみんな僕のひざの高さぐらいの身長の、糸で操られる人形たちばかり。
出し物は、河竹黙阿弥の「勧善懲悪覗機関村居長庵」という歌舞伎の戯曲を、山元清多さんが「破れ傘長庵」という題名にして、脚色演出したもの。
僕は悪人・村居長庵に扮して、小さな人形たちを騙したり、殺したり、金を盗ったり、あげくは何人もの人形たちを相手に大立ち回り、舞台狭しと暴れまわり、刀で切りまくるのです。といってもねえ、相手は人形ですからねえ。ちょっと大人げないというか、馬鹿みたいな気にもなるのですけど、そこはやっぱり役者ですから、だんだんむきになってくるのです。
今、急に、そういえば、ポール・ギャリコの『七つの人形の恋物語』というお話があったなあ、と思い出した。たしか、女優だか芸人をめざしていた女の子が、どこでもうまくいかず、川に身投げをしようとしたとき、人形劇一座の人形に話しかけられ、その一座の仲間になって、興業に参加するんだ。ほとんど人形たちと同等の立場になってね。友だちのようになり、慰めあったり、励まされたり。
ところがときどき、一座の座頭で人形遣いの男が、彼女にひどく冷たく当たって意地悪をする。そこへ、アクロバットだったか綱渡りだかの芸人の男が現れて、彼女に優しくして、とうとう二人は結婚することになり、彼女はその人形一座を去ることになる。人形たちは、彼女と別れるのが寂しくて引き留めようとしたり、彼女の新しい人生を祝おうとしたり、七つの人形たちは葛藤する。でも、そもそも、その人形たちを操っているのは、彼女につらく当たる座頭の人形遣いだと気が付く。彼女が心から愛していたのは、その人形遣いだった、というような話だったと思う。
いや、あまり確かな記憶ではないから、信じちゃダメだよ。でも、読み物の特権で、読んでいると、人形の大きさも人間の大きさも差がなくなって、不思議な錯覚をしてしまう。小説はずるいなあ、芝居じゃそうはいかないものなあ、と悔しく思ったことを覚えている。
『ピノッキオの冒険』という木の人形の物語は、誰でも知っているよね。ディズニーのアニメーション映画が、最も有名かもしれない。でも、原作の挿絵はずっとへんちくりんで、グロテスクで、僕はそっちのほうがずっと好きだ。なんだか悲しいし、子どもってこうだったよ、と思えてくる絵なんだ。
この物語は、19世紀の終わりごろ、カルロ・コッローディという人が、イタリアの子ども新聞に連載したものらしい。途中で終わって、評判がいいのでまた続けて、死んだ人をまた生き返らせたり、何だかつじつまなんかあんまり合ってないんだけど、それがかえって、子どもが生きていく感覚、自分の子どものころの記憶に似てるような気がして、僕は好きなんだ。
学校に行くことになっちゃあ、すぐに寄り道して、人形一座に紛れ込んでしまったり、キツネとネコに騙されたり、嘘をついて鼻が伸びたり、ロバになってしまったりするんだけど、その度に、「これからは、いい子になる」と約束して、またその約束を破ってしまう。そして最後は、自分を作ってくれたゼペットさんと、フカの腹の中で再会する。
子どものころの時間はとても長く感じて、いつまでたっても大人になれないような気がしていた。人生というものは、なんだかうんざりするほど長いんだなあ、と思っていた。ところが、大人になると、時間はものすごいスピードで流れていく。僕はいったいいつから大人になったのだろう? いつから人生がそんなに長いものではないと感じるようになったのだろう?
ゼペットさんと再会したピノッキオは、一生懸命この世の中で良いこととされていることをして、とうとう本物の人間の子どもになる。そのとき、ゼペットさんにこんなことを言う。
「ねえ、父ちゃん、前の木の人形の僕は、どこへいっちゃったの?」
すると、ゼペットさんはうれしそうに、「ほらあそこだよ」と部屋の隅を指すと、そこに、大きな操り人形が不格好な姿で転がっている。
僕は『ピノッキオの冒険』という、お話のつじつまの合わないようなどの場面も、なんだかとてもリアルな子どものころの記憶に思えるのだけれど、この最後の風景だけは、ものすごく不思議で、理解しようとすると、とても怖くなる。
ある日、家に帰ってみると、自分が昨日までの自分ではないような気がして、親にたずねると、「昨日までのおまえは、あそこにあるよ」と言われる。見ると、感情も思考力もない人形が転がっていて、確かにそれは自分のような気がする。確かに自分には人形だった記憶しかない。
ね、怖いよね。とにかく僕は自分自身のぬけがらをそんな風に眺めたことはない。
結城座の人形と芝居をして、僕はむきになって人形に悪態をついたり、小突いたりしたけれど、ときどき落ち着かなくなって、その人形を操っている結城孫三郎さんの顔を見てしまう。何本もの糸を巧みに操っている孫三郎さんがその人形の正体なんだと納得して、また安心して芝居を続ける。