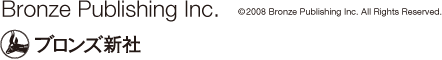朝、ボーヴィルの家で、それぞれ自分で朝ごはんを食べる。僕はグレープフルーツジュースと、バケットにバターとタラモか、コルシカ島のママレードを塗って食べる。野菜不足になるので、二十日大根ポリポリ。あとはコーヒー。そしてタゲ氏かミュージシャンの車で、アミアンまで20分ぐらい飛ばして、劇場に入る。みんなはもっと早くから、それぞれ身体を温めるためウォーミングアップをしている。頃を見計らってその日の題材を提案し、サーカスとしての表現を探る作業が始まる。
朝、ボーヴィルの家で、それぞれ自分で朝ごはんを食べる。僕はグレープフルーツジュースと、バケットにバターとタラモか、コルシカ島のママレードを塗って食べる。野菜不足になるので、二十日大根ポリポリ。あとはコーヒー。そしてタゲ氏かミュージシャンの車で、アミアンまで20分ぐらい飛ばして、劇場に入る。みんなはもっと早くから、それぞれ身体を温めるためウォーミングアップをしている。頃を見計らってその日の題材を提案し、サーカスとしての表現を探る作業が始まる。
お昼休みは、1時頃から2時半まで。10分ぐらい歩いて行ったところにある公務員のための食堂で、とても安い定食を食べる。公務員ばかりがお盆を持って並んでいる。もちろん日本の公務員と違って、ネクタイしている人はほとんどいない。並びながらいつもいつも同じ顔ぶれが、同じ顔ぶれとべちゃべちゃべちゃべちゃ話をしている。そして毎日同じようなものを食べている。食べている間も、ずっと話をしている。はじめのうちはその風景がとても面白く、その風景の中に自分も混ざっていることがおかしかったが、だんだん飽きた。料理もすっかり飽きたが、時間になると、ちゃんとお腹がすいて食べてしまう。
夕食は、8時頃。劇場の横に付いているレストランで食べる。ものすごく太った主人が、難しい顔をして料理を運ぶ。前菜が出る日は、デザートがでない。前菜が出ないと、みんな喜ぶ。でも、デザートのかわりにチーズが出る日は、みんながっかりする。
10日過ぎた27日夜、妻の明緒が到着して、それからちょっと食生活が変わった。そうめんや梅干し、海苔とか日本の食材を少しずつ持ってきたのだ。お米はこっちではサラダに使うイタリア米が比較的日本のお米に近いと聞いて、それを炊いてみる。なんとアケミさんが炊飯器を持ってきていたのだ。彼女はフランス人と結婚していて、もうずっとこっちにいるのだが、食事はそれぞれ自分の食べたい物を勝手につくって食べると言っている。でも、彼女たちはとても仲が良いんだ。
明緒は健康面でも好みの面でも、食事にはとても気を遣う。僕は美味しいものはなんでも食べたくなる。珍しいものやその土地にしかないもの、その人が特別につくったものは食べたい。要するに、くいしん坊なんだね。だから外国に行くと、必ず太る。旅公演なんかでも太らないようにするのは苦労がいる。フランス人は美味しいものが好きな人が多いので大変だ。
明緒が朝、そうめんをつくってくれた。だけど箸がない。仕方がない、フォークで食べるかと言う。それはとても悲しいことだ。庭に出て、こっそり木の枝を包丁で切り落とし、さっさと削って箸を2膳つくる。明緒は「現場に強い男!」とか言って喜んでいるが、家主に見つかったらどうしようと、少しドキドキした。昔、フランス映画で『木靴の樹』というのがあって、子どもが学校に通うのに靴がない親が、地主の所有する樹を切って木靴をつくって、村を追い出される。その場面を思い出したのだ。フランスの木の枝でつくった箸は妙に風情があって、朝のそうめんはとても美味しかった。
![]()
 サーカス芸人はスポーツ選手みたいなところがあって、まず自分のコンディションを整えないと稽古にならない。いつも僕がつきあっている日本の舞台俳優とは、ずいぶん様子が違う。少し長い時間話をして、さあやろうと言うと、体が冷えてしまったからすぐにはできないという。そんなものかと言う通りに聞いていると、そんなことばかり言いだす。それに、僕にはどうも本気を出しているようには思えない。
サーカス芸人はスポーツ選手みたいなところがあって、まず自分のコンディションを整えないと稽古にならない。いつも僕がつきあっている日本の舞台俳優とは、ずいぶん様子が違う。少し長い時間話をして、さあやろうと言うと、体が冷えてしまったからすぐにはできないという。そんなものかと言う通りに聞いていると、そんなことばかり言いだす。それに、僕にはどうも本気を出しているようには思えない。
とうとうしまいに、「君らが必要ならいくらでも準備の時間をあげるから、やるときはきちんとやってくれ」と強い口調で言ってしまった。なにしろ、フランス語の通訳を通しているので、言葉の意味だけに頼っても、こっちの気持ちはなかなか通じないようなのだ。だからときどき、床を蹴ったり、大きな声を出さないと、気持ちが伝わらないということがわかってきた。
40歳のクリフトフと35歳のミッシェル以外は、本当に若い。サーカス学校を卒業したばかりの22、23歳の子、せいぜい25、26歳の子なので、現場の厳しさをあまり知らないようなのだ。
まあ、サーカスの技は失敗したら大けがをするものが多いし、死んだ人だってたくさんいるのだから、神経質になるのは仕方がない。
![]()
朝早く起きて、村の中を散歩する。運動不足を補うためもあるので、背筋を伸ばしてせっせと歩く。あまりそんな風に歩いている人はいないので、たぶん村の人は奇妙に思うのかもしれない。車が止まって、「どこまで行くのだ? 乗っていくか?」と聞かれたりする。たいていは無愛想な顔でじっと見ているので、「ボンジュール!」と言うと、前からの知り合いのように「ボンジュール」と返す。
知らない村や畑の中、森に沿った道を、ただただ歩くのはものすごく楽しい。古い家の構造や、崩れかけた屋根瓦、垣根の植木、生活の具合、干してある洗濯物、突然現れるロバや羊。頭の中に音楽が流れ、いろいろな想いや感覚、感情が自由に動き回るのを感じる。自分が昔の旅人だったような気持ちになる。そうだ、旅をするというのはこういうことだったんだ、と思いだす。そして自分は、ずっと旅をしているんだと思う。
![]()
ジャグラーのミッシェルは、もう17年間ジャグリングをしている。5本のピンを何分間でも宙に舞わせる。彼が少年に近い頃、会ったことがある。その頃から天才ジャグラーで、休み時間でも食事の時間でも、身の周りにあるものを手当たり次第に空中に投げ、嬉しそうにジャグリングをしていた。それなのに今、彼はあまりジャグリングに熱意を感じていないようなのだ。「ミッシェルの見せ場をつくろうぜ」と言っても、苦笑いするばかりで、あまり乗ってこない。別のことをやりたいらしく、変な仕掛けをつくって乗っかってみたり、持ち上げてみたり、ひとりで怪しい実験をしているのだが、あまりうまくいかない。それより、若い芸人たちに指導しているときのほうが楽しそうなのだ。
団長のタゲ氏は、「ジャグラーがジャグリングをしないでどうするんだ。」と苦い顔をしているが、それこそ十数年の付き合いなので、きついことは言いにくいようなのだ。 彼はみんなと一緒にボーヴィル村の宿舎には泊まらず、「シルク・ド・ジュール・ヴェルヌ」の楽屋口に駐車したトレーラーにひとりで寝泊まりしている。変な奴だなあと思うけど、サーカスの連中には普通のことなので、誰も何にも言わない。彼はもう何年もその中で暮らしていて、2回結婚して、それぞれに子どもがいて、その子たちもトレーラーハウスで育って、母親と出て行ったらしい。最近別れた女性との子どもは5歳のトム。壁に写真がいくつも貼ってある。終りの10日間ぐらい、トムが来た。トムは、父さんミッシェルにずーっとくっついて離れない。2人でトレーラーハウスの中で暮らしていた。子どもと犬がそろうと、あーサーカスだなあと思う。
彼はみんなと一緒にボーヴィル村の宿舎には泊まらず、「シルク・ド・ジュール・ヴェルヌ」の楽屋口に駐車したトレーラーにひとりで寝泊まりしている。変な奴だなあと思うけど、サーカスの連中には普通のことなので、誰も何にも言わない。彼はもう何年もその中で暮らしていて、2回結婚して、それぞれに子どもがいて、その子たちもトレーラーハウスで育って、母親と出て行ったらしい。最近別れた女性との子どもは5歳のトム。壁に写真がいくつも貼ってある。終りの10日間ぐらい、トムが来た。トムは、父さんミッシェルにずーっとくっついて離れない。2人でトレーラーハウスの中で暮らしていた。子どもと犬がそろうと、あーサーカスだなあと思う。
犬はクロという、タゲ氏のパートナーのまゆみさんがかわいがっている毛むくじゃらの犬。ひょうきんものの猟犬なのでなんでも追いかけるが、サーカスの稽古の中には決して入らない。

明緒は途中、ひとりでパリへいって、伝手を頼って画廊を回り、自分の写真作品を見てもらって、断られたり、興味を持たれたり一喜一憂して帰ってきた。でもどの人も、表現の意図をすぐに的確に理解してくれると言っていた。
ベルリンでもルーマニアのシビウでもそうだったが、彼女の写真を見た人たちの感想を聞くのは面白い。ほとんどの人が曖昧に「いいじゃない」「素敵ね」などとは言わない。自分流の言い表し方で自分の感想を言う。
![]()
3月中旬、アミアンに着いた頃は気候が悪く、ときどきみぞれが降ったり、暗くてどんよりとした寒い日が続いていた。「これが北フランスの気候だよ。夏だってこんな日があるんだよ」と言われ、だんだん気が滅入ったりもした。でも4月になり、晴れ渡った日があったり、少しずつ暖かくなって、ゆっくりだがわかりやすく春になってきて、気がつくと緑が増え、花が咲き、人々は外に出て日差しの中でお茶を飲んだりしている。
気がつくと、僕らのサーカスもだんだん願っていた姿を現し、色合いがでてきた。