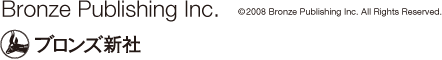去年10月5日、緒形拳さんが亡くなった。お葬式は身内だけということだったし、僕は松本で公演中だったので、お別れはできなかった。今年になって、お別れ会をやるという知らせがきたが、『ピランデッロのヘンリー四世』の初日数日前で、予定を見ると「劇場入り場当たり稽古」と書いてある。あー、無理だ。行けない!
複雑な気持ちのまま、そのことを心の隅に押し込んで、『ヘンリー』の稽古をしていた。ある日、稽古場の廊下に貼ってある予定表を見なおすと、なんとその日がオフになっている。え!? 大道具を仕込むための日になったのだ。僕がそのとき着ていた稽古着のTシャツの胸元を見ると、「Waiting For Godot」と書いてあった......緒形さん、緒形さんが、無理やり休みにしてくれたんだな。
これだけ書いただけでは、たいていの人にはわからないや。
![]()
何年も前、僕が30年間続けた劇団「オンシアター自由劇場」を解散して、 「Bunkamuraシアターコクーン」の芸術監督の仕事も任期が終わったので、ちょうどいいや、と思って、少しどこか遠いところで、芝居の世界から離れてのんびりしてみようと思った。当たり障りのなさそうなロンドンに、1年ぐらい滞在することにしたんだけど、結局、気がついたら、「ゲイトシアター」というところで、演出をしたり、ワークショップをしたり......おいおい、ちっとも芝居から離れないじゃないか、と自分であきれたんだけど、そのワークショップに、どういうわけか、緒形さんがやってきて参加したんだ。ベセナルグイーンとかいう下町の古いビルだけど、気持ちのいい稽古場でね、いろんな国の人たちが集まって、威勢のいい若い役者や大学の先生みたいな人や、ボスニアのほうから亡命してきた人や......とにかくいろんな人がみんな子どもみたいになって、まあ、遊んでるようなもんだったんだけどね。
「ねえ、緒形さん、なんでこのワークショップに参加することにしたのさ?」
「うーん......ちょうどこっちに来たしな、お前が変なことやってるなと思ってさ」
「ふーん」
そんなことがあって、何か一緒に芝居をつくろうかということになって、1年ぐらい後かな、僕が『ゴドーを待ちながら』を持っていくと、
「これ面白いのか?」
「うん、読んでも面白くないかもしれないけど、緒形さんと僕とでやったら、きっと面白いと思うよ。うん、かなり面白い芝居になるような気がする」
「そうか。じゃあ、やるか」
そんな感じで、僕らの『ゴドーを待ちながら』は始まった。

考えてみると『ゴドーを待ちながら』という芝居は、長い間、ずーっと心のどこかに引っかかっている芝居だった。たしか、高校生の頃、「文学座」のアトリエ公演で観たのが最初だったかな。
舞台の真中に、オブジェみたいな木が1本立っていて、山高帽子をかぶった男が2人、とりとめもない会話をとりとめもなくしていると、やたらに威張ったかっぷくのいい男が、ロープにつないだ痩せた下男のような男を連れてやってくる。高校生の僕には、難解な芝居ではなく、むしろ、おしゃれな心地よい前衛劇に思えたな。
劇団「民藝」で演ったのも観たし、セントルイスという漫才の人が演ったのも観た。外国でもいくつか観た。それよりなにより、前にも書いた通り、「自由劇場」の旗揚げ第2弾の演目は、最初『ゴドーを待ちながら』だった。当時のレパートリーポスターというのを見ると、『イスメネ・地下鉄』の下に、ちゃんと『ゴドーを待ちながら』が並んでいる(それが、上演権の関係で、今演っている『ヘンリー四世』に変わったわけだ)。
僕だけではなく、『ゴドー』は1953年にパリで初演されて以来、世界中の演劇にかかわる人たちが無視できない芝居になった。日本でも、僕より若い世代の人たちが、オマージュのような、パロディのような作品をいろいろ書いている。ところが、実際に上演するとなると、どうもうまくいかないようで、ただ小難しい芝居になってしまう。サミュエル・ベケットの不条理劇などと言って、みんなが難しいことを言い並べるものだから、演じるほうもつられて、必要以上に難しく考えてしまったような気がする。そのうちに、なんとなく古臭い芝居にさえ思えてきて、まともに上演するのは気恥ずかしいような時期もあった。ブレヒトなんかもそうなんだけど、芝居として魅力的なものを研究者のような人たちが、ああだこうだ論じて、その影響で、どんどん小難しいつまらないイメージで固められてしまう芝居があるんだよなあ。
![]()
緒形さんと僕の『ゴドーを待ちながら』も、はじめのうちは、ずいぶん戸惑った。だいいち、台詞がちっとも頭に入らない。どうやら役者というのは、自分の台詞の根拠を見つけないとしゃべれないらしい。それに、そうしろと教わってきた。意味も考えずに、ただ丸暗記してしゃべってはいけないということは、当たり前のように身につけてきた。でも、実際に生きている人間は、そうとばかりはいえない。根拠もなくしゃべることだってたくさんあるし、自分の発した言葉をすべて解釈できるわけではない。ま、要するに、そんなことを考えさせられてしまうような、とりとめもないような、でも、意味深な短い言葉のやりとりが、長々と続くのだ。
「さあ、もう行こう」
「だめだよ」
「なぜさ?」
「ゴドーを待つんだ」
「ああそうか。(間)確かにここなんだろうな?」
「何が?」
「待ち合わせさ」
「木の前だっていってたからな。ほかにあるかい?」
「こりゃ、なんだい?」
「柳かな」
「葉っぱはどこだ?」
「枯れちまったんだろう」
「涙も尽きてか?」
「でなけりゃ、季節のせいだ」
「だが、こいつはどっちかっていったら、灌木じゃないか?」
「喬木だよ」
「灌木だ」
「きょうー、そりゃ、いったい、どういう意味だね? 場所を間違えてるとでもいう気かい?」
「もう来てもいいはずだからな」
「しかし、確かに来ると言ったわけじゃない」
「じゃあ、来なかったら?」
「あした、もう一度来てみるさ」
「それから、あさってもな」
「そりゃあ......そうさ」
「その調子でずっと」
「だからそれは......」
「やっこさんの来るまで」
「おまえ、なにもそう......」
「おれたちは、きのうもここへやって来たんだぜ」
「いいや、そりゃ違う」
「じゃあ、きのうは何をした?」
「きのう、何をしたって?」
......台詞を写していたら、止まらなくなっちゃった。
最初に「Bunkamuraシアターコクーン」の稽古場で、お客さんを入れて試演会のようなことを演ったときは、大変だった。どっちかが台詞をちょっと飛ばすと、もうどこへいっちまったのかわからなくなって、いい加減なことを言うと、いきなり2幕に飛びそうになったり、もとに戻ってしまったり......終わって、2人とも、すごく傷ついてね。僕は大人げなく喚いてしまうし、緒形さんは楽屋の奥から出てこないし、険悪になって、もうこれでこりごり、二度とやらないかと思った。
でも、考えてみれば、やっぱり緒形拳という役者は、とてつもなく素敵な俳優なんだ。何十年もやってきた名優といわれる大スター俳優が、自分の安全地帯から飛び出して、やらなくてもいいような危険な冒険を引き受けて、みんなの前で大恥かくなんてさ、どうだい、おいそれとできることじゃあないんだよ。

それから、長いながい『ゴドーを待ちながら』の旅が始まったんだ。
足掛け5年かな? 九州から北海道まで、ずいぶんいろんなところで演ったなあ。いわゆるきちんとした劇場施設ばかりでなく、いろんな空間で演った。舞台装置は、客席の真中に廊下みたいな舞台が横切っていて、中央が少し広くなっている。一本道の途中で、ゴゴとディディが、ゴドーという誰だか分らない人を待っているのを、観客は両側から観ている。
全体が古いトラックのシートみたいな布で囲われていて、一方の客席の後ろの布には「Waiting For Godot」という文字と、葉のない1本の木をゴゴとディディが眺めている簡素な絵が描いてある。だから、原作に指定されている舞台の上の1本の木はなくて、そっちのほうを向いて、無対象の芝居をする。片方の出入り口は簡素だが、もう片方は昔のボードビルショウみたいな電飾の裸電球がいくつも付いている。なんだか安っぽい見世物小屋のような、田舎を回る小さなサーカスのテントの匂いを感じる空間。
あるときは、「Bunkamuraシアターコクーン」の舞台の上に、客席も何もかもつくって演ったことがある。舞台の緞帳は閉めて、お客さんは楽屋口から入る。コクーン(繭)の中にあるから、スタジオピューパ(蛹)なんて名付けてね。芝居の出入り口の一方は道具の搬入口だから、本当の渋谷の街、反対側の出入り口は緞帳の向こうへ入るから、本来の劇場の観客席。僕らは、現実社会と虚構世界の狭間で芝居をしているようで、楽しかった。
水戸の芸術館も、なかなか贅沢な劇空間になった。なったというのは、劇場というのは、使い方でずいぶんイメージが変わるものなんだ。どんなところでも、その空間が本来持っている魅力を見つけ出すと、突然素敵な劇空間に変貌する。
『ゴドー』の旅は、そのことを発見する旅でもあった。
とくに、北海道の小さな町に残っている石倉、以前は穀物などをしまっておく石造りの小屋だったものを再利用して、スタジオや画廊のようなものにしているところがいくつもあって、そういうところを中心に回ったことがある。倉庫といっても、いろいろな形や大きさがあるから、行く先々で出入りの方法や芝居の位置を変えなければならない。真四角で、道になる空間がやけに短いところもあれば、細長い舞台になってしまうところもあった。
はじめのうちは、その度に苦労したが、だんだん臨機応変に演技空間をいろいろ変えていくのが楽しくなってきた。立ち位置や引っ込みの方向が分らなくなったりしても、それがこの『ゴドーを待ちながら』という芝居らしく、自分たちの混乱を芝居として楽しめるようになってきた。
つまりこの芝居で、ゴゴとディディは、たぶん毎日のように道端のどこか1本の木が立っている場所で出会って、ゴドーを待ちながら、時間をつぶしているのだが、それが昨日と同じ場所なのか、確かに昨日ふたりは会ったのか、なんだかわからなくなってしまう。
ぼくたちもまた、昨日芝居をしていた場所と、今日自分たちが立っている空間がどう違うのか、よくわからなくなってくるんだ。緒形さんは、舞台裏に引っ込むなり苦しそうな目つきで、「ここはどこなんだ!」なんて、ほとんどゴゴの台詞のようなことをいう。
老人施設で演ったことがある。看護婦さんが付き添った車椅子が、何台も並んでいる。みんなつまらないのか、眠っているのか、下を向いているような気がする。誰かが「おしっこ」と言うと、連鎖反応で半分ぐらいの人たちが看護婦さんと一緒にトイレに行ってしまう。演りながら、すごく、焦る。芝居もいつもよりだんだんオーバーになって、わかりますかー?こういうこと、演ってるんですよー、みたいなオセッカイな芝居になってくる。一幕が終わって、げんなりして楽屋に戻ると、係りの人が、
「みんな、すごーく、楽しんでますよ。感動してますよ」と言う。
「あの人たちが、首を真っすぐして舞台を観つづけけるということは、健常者が片足で立って観ているようなものなんですよ。クスクスッと笑うのは、普通の人の大爆笑と同じ反応なんですよ」
......僕らはとても恥ずかしくなって、いつもの通りやろうねと、お互い無言で合図を送って、舞台に向かった。拍手は静かだったが、とても熱い拍手だった。終わると、何人もの老人が、人懐っこく周りに集まってきた。
「緒形さん、死んだあたしの亭主にそっくりよ」
みんなが、かわいい声でクスクス笑う。

青物市場で演ったことがある。まだ、キャベツや大根の匂いが残っている。スタッフは突貫作業で、大きな天窓に黒い幕を張る。仮設の照明機材を吊るのに、四苦八苦する。市場で使っている大きな箱なんかを利用して、階段状の客席ができてくる。いつもの「Waiting For Godot」と書かれたトラックシートが吊るされると、もうすっかり『ゴドーを待ちながら』のための劇場だ。近所のおかみさんや子どもたちや犬までが、物珍しそうに覗きにくる。緒形さんが出てきて、みんなをからかったりしている。明るい夕方。
「おまえと暮らすのはむずかしいな、ゴゴ」
「別れたほうがいいかもしれない」
「おまえは始終そう言う。そして、そのたびに、すぐまた帰ってくるんだ」
・・・・・
「何を言っているのかな、あの声たちは?」
「自分の一生を話している」
「生きたというだけじゃ満足できない」
「生きたってことをしゃべらなければ」
「死んだだけじゃ足りない」
「ああ足りない」
・ ・・・・
「ちょうど、羽根の音のようだ」
「木の葉のようだ」
「灰のよう」
「木の葉のよう」
──長い沈黙──
「なんか言ってくれ」
「今探す」
──長い沈黙──
「なんでもいいから言ってくれ!」
「これからどうする?」
「ゴドーを待つのさ」
「ああそうか」
青物市場の天井の幕がめくれる。夜空に本物の月。
![]()
 ああ、『ゴドーを待ちながら』の旅の思い出は、尽きない。ポツォー役とラッキー役は、大森博史さん田中哲司さんから、朝比奈尚行さん小松和重さんに変わった。それと男の子の役がハッピー。役者はいつもその5人。
ああ、『ゴドーを待ちながら』の旅の思い出は、尽きない。ポツォー役とラッキー役は、大森博史さん田中哲司さんから、朝比奈尚行さん小松和重さんに変わった。それと男の子の役がハッピー。役者はいつもその5人。
それから、ほとんど一緒だったのが、息子の十二夜。はじめの頃、まだ歩けなくってね、『ゴドー』と一緒に、大きくなったんだ。緒形さんもみんなも、マスコットみたいに、かわいがってくれたなあ。
博多の海。オホーツク海。羊の牧場。知床半島のトドワラ、ナラワラの不思議な湿地帯。マイクロバスに乗ったり、汽車に乗ったり。
あの頃、僕たちの旅は、もう『ゴドーを待ちながら』という芝居の一部のように思えてね。こうやっていること全部が、『ゴドーを待ちながら』なんだなあ、と感じてた。たぶん、みんな。
緒形さんは「これは、ゴドーを探す旅なんだなあ」なんて言っていたし、僕は、そうなら本気で探さなければと思って、もっと先の旅の計画を立てていたのに、緒形さんはひとりで遠くへ行ってしまった。
![]()
『ピランデッロのヘンリー四世』の稽古オフの日、緒形さんのお別れの会に出かけていくと、赤坂の大きなホテルに、それは大勢の人たちが集まっていて、緒形さんの偉大な業績、映画やテレビの仕事の写真がたくさん飾ってあって、その中に『ゴドーを待ちながら』の写真も1枚ちょこんとあって......ちょっと、なんて表現していいのかわからない、奇妙な気持ち......切ないような、こっそり誇り高いような......。
「やあ、おまえ、またいるな、そこに」
「そうかな?」
「うれしいよ、また会えて。もう行っちまったきりだと思ってた」
「おれもね」
「何をするかな、この再会を祝して......立ってくれ、ひとつ、抱擁しよう」
「あとで、あとで」
![]()
『ゴドーを待ちながら』の最後の公演は、2004年4月、松本のあがたの森にある、旧制松本高校の古い講堂だった。木造の立派な建物で、僕らは古風なシャンデリアの下で、芝居をした。最後の公演の開演前、緒形さんとふたりで、ゴゴとディディの衣裳のまんま、表に出た。今は公園になっている旧制高校の校庭には、大きなヒマラヤ杉が立ち並んでいて、見上げると、4月だというのに、鳥の羽のような牡丹雪がひらひら、ひらひらとめどもなく降ってきて、僕らは、ただただ空を見上げていた。